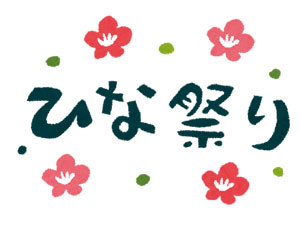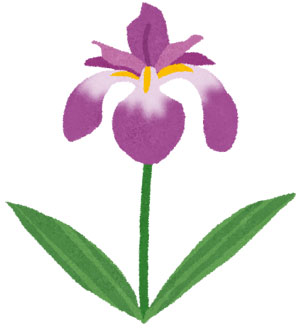
端午の節句は菖蒲の節句とも呼ばれます。
なぜ、そんなふうに呼ぶんでしょうね。
また、5月5日の端午の節句には、
菖蒲湯に入るようなのです・・・
端午の節句は知ってますが、菖蒲の節句(しょうぶのせっく)は、
ちょっと聞き覚えがなかったので、とても気になりました。
それに菖蒲湯(しょうぶゆ)なんてもっと気になります。
そこで今回は菖蒲の節句について、
- なぜ菖蒲の節句なのか?
- 菖蒲湯とは何なのか?
を調べてきましたよ。
それでは、まずは菖蒲の節句とは?
菖蒲の節句とは
端午の節句は、月の端(はじめ)の午(うま)の日との意味ですが、
この午(ご)と五(ご)の音が同じことから5月5日になったといわれます。
古代中国では、5月の最初の午の日に蓬(よもぎ)で作った人形を
間口に掛けて、菖蒲に浸した酒を飲み、災厄を祓ったそうです。
日本でも奈良時代には貴族が、身の穢れを払う行事として、
菖蒲や蓬などを摘んで臣下に配ったり、軒先に挿していました。
そして鎌倉時代になると武家社会となり、菖蒲は尚武・勝負などとかけて、
武士を尊ぶ「尚武(菖蒲)の節句」となってゆきます。
このような理由から「端午の節句」は「菖蒲の節句」とも呼ばれています。
では、菖蒲湯と何なのでしょうか?
菖蒲湯とは?
菖蒲は昔から、その香りの強さで邪気を祓うと言われており、
軒先に挿して魔除けにしたり、お酒に浸して菖蒲酒に使われてました。
そして菖蒲を風呂入れた菖蒲湯に入り、体の災厄を祓っていました。
しかし菖蒲湯には、ちゃんとした効果・効能もあります。
- 肩こり
- 腰痛
- 神経痛
- 筋肉痛
- リュウマチ
- 冷え性
- 血行促進
菖蒲に含まれるオイゲノールやアザロンといった精油成分が、
腰痛や神経痛などの痛みをやわらげる効果があるのです。
また、菖蒲の強い香りは心身をリラックスさせる効果もあるといわれます。
こんなにもナイスな効果・効能があるなら、ぜひとも入らないとダメですね。
むしろ5月5日じゃなくても菖蒲湯に入ろうと思いましたよ。
では、菖蒲湯の作り方は?
菖蒲湯の作り方はいたって簡単です。
この季節になると、花屋だけでなくスーパーなどでも菖蒲が売っています。
だた、よく似た「花菖蒲」は違うので購入する前に確認して下さい。
それでは作り方です。
- 菖蒲を10本程度に輪ゴムなどで束ねる。
- 空の浴槽に束ねた菖蒲を入れる。
- お湯の温度を熱めの43度ぐらいにして入れる。
- あなたの適温に冷ましてから入浴する。
たったこれだけなので、菖蒲さえあれば簡単に作れますね。
熱めのお湯で入れるのは、そのほうがしっかりと香りが出るからです。
管理人は熱い湯が好きなので、43度でもへっちゃらですが、
熱いのが苦手な人は、十分に冷ましてから入浴して下さいね。
菖蒲のない時期でも、これがあれば菖蒲湯が楽しめます。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。